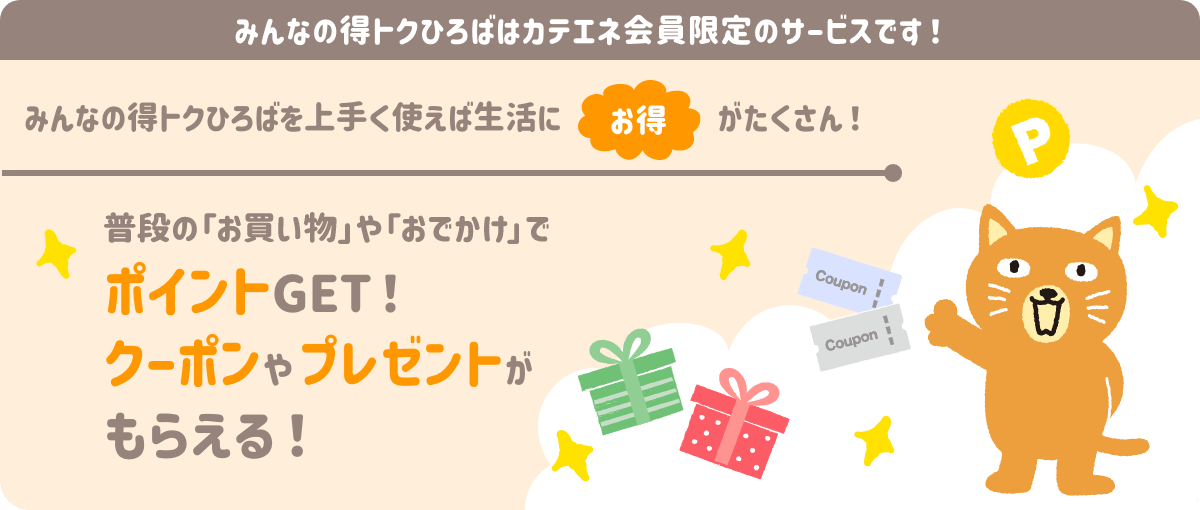毎月2回更新
プレゼントコーナー
アンケートに答えてプレゼントGET
もっと見るお買い物でポイントコーナー
ネットショッピングでカテエネポイントGET
もっと見るソトエネコーナー
店舗に行くとポイントがもらえる!
もっと見る
{{#list}}
{{/list}}
優待情報
お得な会員限定の情報をGET!
カテエネ会員限定のお得な情報を数多く掲載!
東海地方で人気のレジャー施設や宿泊施設などの優待情報を
カテエネ会員さま限定で掲載!
詳細ページで限定特典の受け取り方をチェックしてお得な特典をGET!
アンケートコーナー
アンケートに答えてカテエネポイントGET
※アンケートコーナーをご利用いただくためには、TC IDにてログインしていただく必要がございます。
※アンケート内容に関するお問い合わせは こちら(GMOリサーチ株式会社)
※ご質問・お問合せは、メールにて承ります。
※お電話でのご質問・お問合せは受付けて おりませんので、あらかじめご了承願います。
アンケートコーナーへ